「最近お腹周りが気になる」「健康診断でメタボを指摘された」
このような方はいませんか?メタボ(メタボリックシンドローム)は、内臓脂肪の蓄積に加え、高血糖・高血圧・脂質異常のうち2つ以上が当てはまる状態です。メタボを放置すると、血糖値が慢性的に高くなり、2型糖尿病の発症リスクが高まります。
どのようにすれば、2型糖尿病を予防できるのでしょうか。本記事では、糖尿病の基本知識や腎不全との関係、予防法について解説します。
 はる
はるこの記事は次のような方におすすめ!
・メタボと指摘された方
・糖尿病の効果的な予防法を知りたい方
糖尿病とは?
インスリンと血糖値の関係や、糖尿病の種類について見ていきましょう。
インスリンと血糖値の関係
糖尿病は、インスリン(血糖値を下げるホルモン)が十分に働かず、血糖値が高い状態(高血糖)が続く病気です。十分に働かない状態には「膵臓から分泌されるインスリンの量が不足する」「インスリンが効きにくくなる」の2つがあります。どちらの場合でも、インスリンの働きが低下するため、細胞が血液中のブドウ糖を十分に取り込めず、血糖値が高くなります。
- のどの渇き
- 水分摂取の増加
- 尿の回数の増加
- 体重減少
- 疲れやすさ
- 意識障害
高血糖が続くと、心筋梗塞や腎不全、脳梗塞などの大きい病気につながるだけでなく、失明や足の切断など重い障害を残す可能性もあります。
糖尿病の種類
糖尿病にはいくつかのタイプが存在し、代表的なのは1型糖尿病と2型糖尿病です。
1型糖尿病
体内の免疫システムが、膵臓のβ細胞(インスリンを作る細胞)を誤って異物と認識し、破壊します。その結果、インスリンがほとんど分泌されなくなります。
2型糖尿病
2型糖尿病の原因は、生活習慣(肥満、食べ過ぎ、運動不足、喫煙など)の乱れです。その結果、インスリンが十分に分泌されなくなったり、効きにくくなったりします。メタボになると、2型糖尿病の発症リスクが高くなるといわれています。
糖尿病で腎不全になる?
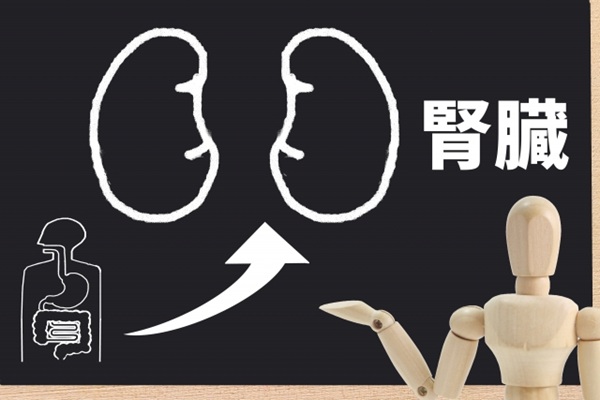
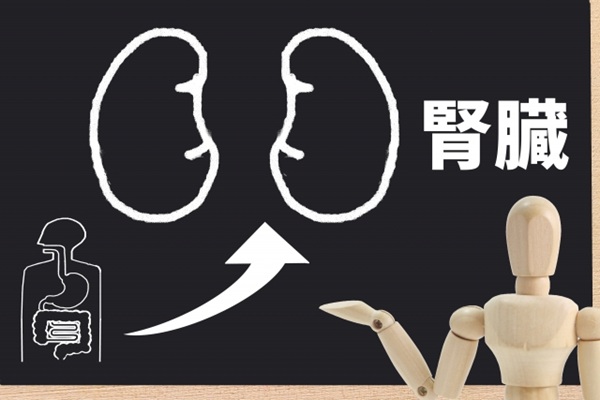
糖尿病による高血糖が続くと、糖尿病腎症という合併症を起こす可能性があります。
腎臓には、糸球体という細い血管の集まりがあります。糸球体とは、血液をろ過し、老廃物を尿へ排出する「ろ過装置」です。高血糖により、糸球体の小さな血管がダメージを受け、詰まりを引き起こし、次第に糸球体が壊れていきます。糸球体が壊れると、血液中のタンパク質が尿に漏れ出し、腎臓の働きが悪くなります。これが、糖尿病腎症と呼ばれる状態です。
糖尿病性腎症の初期は、自覚症状がほとんどありません。しかし、進行すると、体のむくみや高血圧、貧血などが現れます。さらに進行すると、腎臓がほとんど働かなくなる「腎不全」という状態になり、透析が必要になる方もいます。
透析とは、腎臓のかわりに血液をきれいにする治療法です。しかし、長期間にわたる治療であり、体への負担も少なくありません。透析を避けるためにも、早い段階から生活習慣を見直しましょう。
糖尿病の予防法は?
生活習慣を見直すことで、2型糖尿病を予防できるだけでなく、メタボの改善にもつながります。今日から実践できる予防法を見ていきましょう。
適正体重を維持しよう
メタボを改善し、2型糖尿病を予防するには、まず内臓脂肪を減らすことが大切です。そのために、適正体重を維持しましょう。
適正体重は、身長(m)×身長(m)×22で求めます。BMI(体格指数)は、体重(kg)÷身長(m)の2乗で求め、25以上が肥満です。
たとえば、身長1.7m、体重100kgの場合、以下の計算式になります。
適正体重=1.7×1.7×22
BMI=100÷(1.7×1.7)
計算すると、適正体重は63.58kg、BMIは34.60(肥満)です。
自分の適正体重とBMIをチェックしたら、継続的な運動や健康的な食習慣を取り入れましょう。
運動習慣を身につけよう


運動によって、インスリンの働きが高まり、血糖値が安定します。そのため、継続的な運動を心がけましょう。有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせると、より効果的です。
有酸素運動は、ウォーキングやジョギングなどの全身運動を指します。筋力トレーニングは、足や腰、背中の筋肉に負荷をかける運動です。たとえば「壁に両手をつき、かかとを上げ下げする」という動きが、簡単で取り入れやすいでしょう。
ややきついと感じる程度の運動を1回20~60分、週に150分以上行うのが望ましいです。階段を使う、通勤時に一駅分歩くなど、日常生活の中で身体を動かすのも良いでしょう。無理のない範囲で楽しみながら続けると、習慣化しやすいです。
健康的な食習慣を心がけよう
血糖値を安定させるため、過食を避け、バランスの取れた食事を規則正しくとりましょう。
- 間食を減らし、適切な食事量を守る
- 野菜・果物・全粒穀物(玄米、全粒粉の小麦粉、オートミール)・魚・豆類を中心に、バランスよくとる
- 糖分や脂肪分の多い食品は控えめにする
- 1日3回の食事を規則正しくとる
健康を維持するためのサプリが市販されていますが、サプリはあくまで補助的なものです。基本的には食事から栄養をとるようにしましょう。
歯と口腔の健康に気をつけよう


歯周病と2型糖尿病には深い関係があります。歯周病とは、歯肉(歯の根元部分)に炎症が起こる「歯肉炎」と歯を支える骨まで破壊する「歯周炎」の総称です。炎症の原因は、プラークと呼ばれる磨き残しの歯垢です。プラークは、歯磨きで除去できます。
歯周病患者の体内では、絶えず炎症に関わる化学物質が作られ、血流にのって全身に運ばれます。この化学物質が、インスリンを効きにくくし、血糖値を上昇させる原因です。その結果、2型糖尿病の発症リスクが高まります。
歯周病予防が、2型糖尿病の予防にもつながります。毎日かかさず、正しい方法で歯を磨きましょう。また、お口の中のチェックやクリーニングのために、定期的に歯科受診をすることも大切です。
喫煙者は禁煙しよう


喫煙は、2型糖尿病の発症リスクを高めます。これは、喫煙がインスリンの働きを抑え、血糖値を上昇させるためです。さらに、心筋梗塞や脳梗塞などの大きな病気を発症するリスクも高めます。
これらの病気を防ぐためには、禁煙が非常に重要です。喫煙本数が多いほど、2型糖尿病を発症しやすいといわれています。喫煙している方は、喫煙本数を減らすことから始めてみましょう。
自力での禁煙が難しい場合、禁煙外来を利用しましょう。禁煙外来では、禁断症状(禁煙後に現れるイライラやストレスなどの症状)を緩和する薬を処方できます。まずは、禁煙方法について、かかりつけ医に相談してみましょう。
糖尿病を予防して健康な生活を


2型糖尿病を予防するために、まずは生活習慣を見直しましょう。ポイントは「適正体重の維持」です。継続的な運動や健康的な食生活、歯の健康の維持、禁煙を心がけましょう。
2型糖尿病の予防は、メタボの改善だけでなく、心臓や腎臓、脳の大きな病気の予防にもつながります。日々の小さな積み重ねを大切にして、健康な毎日を目指しましょう。
コメント